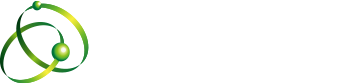交通事故の被害で行う慰謝料請求。しかし、保険会社との示談交渉で、お互いの主張が平行線をたどってなかなか解決しないことがあります。このような場合には裁判で争うことも検討しましょう。
交通事故被害での民事裁判はどのような流れで進むのか、このページでは交通事故の民事裁判の流れについてお伝えします。
慰謝料請求で行う民事裁判について
交通事故の被害に遭うと、通常は相手方の保険会社と慰謝料の交渉を行い、示談での解決を目指します。
しかし、交通事故においては慰謝料の金額などをめぐって被害者側と加害者側が対立することも多く、場合によっては民事裁判を提起することもあります。
この慰謝料請求の裁判について、どのようなものか確認しましょう。
民事裁判と刑事裁判は別のもの
交通事故の慰謝料請求で行う裁判は、民事裁判です。
民事裁判は、民事上の請求権の有無や内容に紛争がある場合に、裁判所でその内容について争われます。
交通事故をめぐる裁判としては民事裁判のほかに刑事裁判もあります。
刑事裁判は交通事故の加害者に刑事罰を課すためのもので、金銭請求とは関係ありません。
加害者の刑事罰を決めることと、慰謝料の金額を決めることは、分けて考える必要があります。
交通事故の損害賠償で争われること
交通事故では何を巡って争われるのかを正確に確認しましょう。
交通事故の被害者は、加害者に交通事故でケガをしたことに対する損害賠償(慰謝料請求)をすることができます。
しかし、この慰謝料請求で保険会社は、被害者が納得するような金額を提示しないことが多いです。
特に、お互いの主張が完全に対立しているケースでは、示談交渉を行っても保険会社が自社に有利な主張を繰り返すような場合もあります。
このようなケースでは示談交渉を続けても歩み寄れませんので、裁判を起こして適正な損害額を裁判所に確定してもらい、相手に支払わせることになります。
交通事故の民事裁判の流れと期間
交通事故で民事裁判を起こす場合の流れと、それぞれのプロセスの中で必要な期間について確認しましょう。
交通事故発生から示談交渉まで
交通事故が発生したらまずはケガの治療にあたります。
特に後遺症が発症するレベルのケガをしている場合、示談交渉を始めるには、いわゆる症状固定と呼ばれるところまで治療することが必要になります。
そのため、ケガの程度や回復次第で、交渉までの期間が前後します。
交渉が始まり、これ以上は交渉による解決が見いだせないとなったら訴訟を起こします。
訴訟の提起から第一回口頭弁論までの流れ
訴訟の提起は裁判所に訴状を提出して行います。
自らの主張を裏付ける証拠と、それらの証拠が何を証明しようとしているかの概略を説明する証拠説明書、住民票などの必要書類とともに添付します。
裁判所で事件の受付がされると、被告(加害者の保険会社)に対して訴状が送達され、被告がこれを受け取ると裁判が係属され(行われることになり)、手続きが進行します。
その後、第一回口頭弁論期日が指定され、その日までに被告である保険会社から、訴状に対する回答である答弁書が送られてきます。
第一回口頭弁論期日は、訴状を提出してから1〜2ヶ月後に裁判所で開かれ、口頭弁論では争点や証拠を整理しつつ、次回までに主張や立証をするように裁判官から促されます。
裁判官が判断するために必要な主張と証拠が出そろうまで、次の期日(口頭弁論の続きを行う場)が指定されますので、その後は、期日で主張と立証を繰り返していきます。
一つの期日は1ヶ月~2ヶ月間隔ごとに進行することになります。
期日が6回開かれれば、裁判が終わるまでに6ヶ月~の期間が必要となります。
訴訟の経過をみながら和解交渉がもたれる
実は民事裁判で判決までいくケースは少なく、多くのケースでは裁判所から裁判の進行状況に応じて和解が提案されます。
裁判が進むにつれて、判決まで行った場合にどのような判決が出るかの見通しがたつことも多いです。
たとえば、過失割合で大きく争っていたときに、過失割合については加害者の保険会社の主張が通らないと見込まれるときに、加害者側が被害者に有利な条件の和解案を受け入れてくれることもあります。
こうして和解をすることができれば、判決を待たずして裁判は終了します。
判決および控訴・上告
和解が調わなければ判決となります。
裁判所は判断をするのに充分な主張・立証が揃うと結審をして、判決を言い渡す期日を設定します。
判決期日に裁判官から判決が言い渡されると、裁判は終結します。
判決内容に納得できないときは、判決言い渡しから14日以内に控訴(第二審)を行うことも可能です。
控訴審も進行は基本的に同じで、不服内容について主張・立証を重ねていくことになります。
控訴審での判決に不服がある場合には最高裁判所に上告することができます。
最高裁判所で判決がされると、判決で下された事実が確定します。
期日内に控訴・上告をしなかった場合も、判決の内容が確定します。

裁判を起こすメリットがあるケース
裁判をすると長い期間がかかることが予想され、また、いろんなことを調べたり、裁判所に出向いたり、書類を提出したりする手間がかかります。
そのため、交通事故の慰謝料請求で裁判をするなら、裁判をしてまで争うメリットがあるか、あらかじめ判断したほうが良いでしょう。
裁判をするメリットがあるケースをご案内します。
重大な人身事故により後遺障害等級が認定されたケース
後遺症が残り、後遺障害等級が認定されたような場合です。
この場合、示談交渉で保険会社が任意保険基準(示談交渉で提示する金額)と裁判基準(裁判をした場合に認められる金額)に大きな金額差が生じることが多いです。
示談交渉で裁判基準の金額、もしくは裁判基準に近い金額に増額できることもありますが、交渉を重ねても裁判基準と大きな金額差があるままの場合もあります。
このようなときは、裁判で争うことで慰謝料を増額できる可能性があります。
「保険会社が逸失利益の支払いを認めない」、「過失割合の主張に大きな隔たりがある」といった場合も、裁判をすることで慰謝料を増額できる可能性があります。
交渉内容が複雑な場合
交通事故において、加害者側と被害者側で争いになる場合は、一つの項目だけで争うことはまれで、複数の項目で争いになっていることがあります。
複数の項目で争うようなことがあると、どの項目についてどの程度争うべきかわからなくなることがあります。
このような場合には、訴訟をすることによって争点や証拠を整理することができます。
そして、本当に争うべきポイントが明確になるので、交渉が平行線のまま長引くよりも、早めに訴訟に移行したほうが、紛争解決がスムーズになることもあります。
裁判を起こす際は弁護士に相談を
交通事故の民事裁判について、お伝えしました。
交通事故の民事裁判によって、行き詰まっている交渉がスムーズに進み、より多くの金額の示談金を受け取ることができる可能性が高まります。
訴訟では、交通事故に関する知識のほか、民事裁判に関する手続きの知識も必要になります。
ここまで弁護士に依頼せずに対応してきた方も、裁判を行う際は弁護士に依頼することをおすすめします。